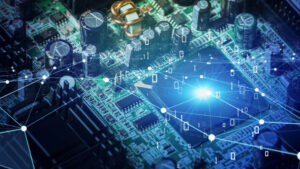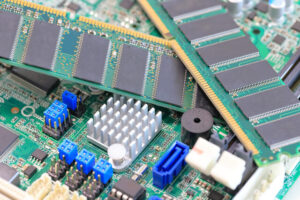アナログASIC設計におけるバンドギャップ基準電圧の基礎と応用技術
アナログASICにおけるバンドギャップ基準電圧(BGR)の役割と設計技術について解説します。温度や電源変動に強い安定性や、構成法、設計上の工夫、応用事例を通じて基礎から応用まで理解できます。
バンドギャップ基準電圧の役割とアナログASICでの重要性
温度や電源電圧の変動が激しいアプリケーションでは、アナログ信号処理の精度を維持するために、変動に強い安定した基準電圧源が求められます。BGRはその役割を担う中核的な回路であり、バイアス生成や基準電圧供給を通じて、各種アナログブロックの安定動作を支えます。信号の整合性や回路特性の再現性を確保するためにも、BGRの導入は不可欠となっています。
電源電圧や温度変動に強い基準電圧が求められる理由
アナログASIC設計において、安定した基準電圧源は高精度な動作の要となります。動作環境において電源電圧や温度が変動する場合でも、基準となる電圧値が変化してしまうと、アナログ信号処理やバイアス生成の精度が著しく低下します。特にセンサ信号処理や電源監視、ADC/DACなどの機能では、誤差が製品全体の信頼性や性能に直結します。このような背景から、温度や電源の変動に対して影響を受けにくい基準電圧の生成が求められ、BGRのような安定したリファレンス回路の重要性が高まっています。
アナログ回路設計におけるBGRの機能的位置づけ
BGRはアナログASIC内の複数の機能ブロックに基準電圧を供給するコア回路の一つです。代表的な用途としては、オペアンプやバッファアンプのバイアス生成、ADCの基準電圧源、また電圧検出やリミッタ回路などのスレッショルド電圧にも利用されます。回路全体のオフセット特性やリニアリティ、安定性に大きな影響を与えるため、BGRの安定性と精度は、アナログASIC全体の品質を左右する非常に重要な要素です。したがって、設計初期段階でのBGR仕様定義とその位置づけは、他の回路ブロックに先行して決定されることも珍しくありません。
高信頼性アナログ設計におけるBGRの影響範囲
高信頼性が求められる産業用や医療機器、車載向けアプリケーションでは、長期間にわたり一定の性能を維持することが必須です。BGRの設計においても、時間経過によるドリフト、負荷変動時の安定性、温度サイクルに対する再現性など、さまざまなストレス条件に耐えうる性能が求められます。BGRが不安定であれば、それに依存するバイアス電圧やしきい値も揺らぎ、最終製品の性能や信頼性に直接悪影響を与えます。このため、アナログASIC設計においてBGRは単なる補助回路ではなく、製品品質の基盤を担う中核回路として設計されます。
BGRの原理と基本構成
BGRは、異なる温度依存性を持つ電圧(PTAT(Proportional To Absolute Temperature)とCTAT(Complementary to Absolute Temperature))を加算することで、温度による変動を打ち消した安定した電圧出力を実現します。Brokaw型のような従来構成から、オペアンプレス型や電流出力型など、用途やプロセスに応じた構成の多様化が進んでいます。出力電圧や温度係数、PSRR(Power Supply Rejection Ratio)などの定量指標を通じて、要求される性能に適合したBGRを選定・設計することが重要です。
PTATとCTAT特性の打ち消しによる温度補償機構
BGRは、温度によって直線的に増加するPTAT電圧と、逆に温度が上がるほど減少するCTAT電圧を加算することで、温度依存性を打ち消します。具体的には、シリコンPN接合のVBE特性がCTAT動作を示す一方で、抵抗とトランジスタの特性を用いて得られる電圧がPTAT動作を示します。これらを適切な比率で加算することで、温度に依存しない基準電圧、すなわちBGR出力が得られます。この手法により、数十℃〜数百℃の広い温度範囲にわたって高い安定性を維持することが可能です。
Brokaw型・オペアンプレス型などの代表的構成
BGRにはいくつかの構成方式がありますが、最も代表的なのがBrokaw型と呼ばれる構成です。これは、オペアンプと2つのバイポーラトランジスタ、および抵抗器で構成され、温度補償を行いながら一定電圧を出力します。一方で近年では、低消費電力化や小面積化を目的として、オペアンプを使用しないオペアンプレス型のBGRも注目されています。これらはシンプルな回路構成で動作するため、低ノイズや高温環境向けのアプリケーションにも適しています。構成の選択は、ターゲットとするプロセス条件や性能要件により最適化されます。
出力電圧、温度係数、負荷/電源変動耐性などの設計指標
BGRを設計する際には、いくつかの主要なパラメータを考慮する必要があります。まず最も基本となるのが出力電圧で、一般的には約1.2V付近に設定されることが多いです。次に温度係数は、その安定性を評価する上で重要で、数十ppm/℃以下を目標とします。また、電源電圧の変化に対する出力変動を示すPSRRや、出力に負荷が加わった場合の電圧変動、すなわち負荷変動耐性も性能指標として重要です。これらの特性をバランス良く達成するためには、回路構成だけでなく、トランジスタの面積比や抵抗値の選定も設計の鍵となります。
アナログASICにおける設計上の制約と工夫
PVTばらつき、雑音、ドリフト、電源変動など、アナログASICにおけるBGR設計には複合的な制約が存在します。性能指標を満たすためには、回路構成だけでなく、トランジスタのレイアウトや抵抗比の精度といったレベルでも設計上の工夫が必要になります。また、低消費電力や小面積といった製品要求を両立させるため、回路構成の簡素化や電流の最適化なども合わせて検討されます。
PVTばらつきに対する設計的アプローチ
半導体プロセスにおけるばらつきは、BGRの出力電圧や温度特性に大きく影響します。設計段階では、MOSFETやバイポーラトランジスタのしきい値、抵抗値の変動を見越したマージン設計が不可欠です。PVTばらつきを吸収するために、トランジスタの面積比や抵抗のレイアウト対称性を活用するほか、シミュレーション時にはMonte Carlo解析を用いて統計的な変動を評価します。また、特定用途ではトリミング機構を設けて出荷時の補正を行うことで、プロセスばらつきに対処します。
雑音・ドリフト・PSRRなどの性能最適化
BGRの出力は、回路全体に広がる基準となるため、雑音特性の最適化は重要です。熱雑音やフリッカーノイズを抑制するために、トランジスタの面積を適切に確保し、電流密度を最適化することが求められます。ドリフト特性は、トランジスタのマッチングや温度依存性によって左右されるため、レイアウト段階での工夫も不可欠です。PSRRについては、電源変動が直接BGR出力に影響を与えるため、カスコード電流源やレギュレータとの組み合わせによって変動を抑制します。これらの設計配慮がBGRの高信頼性を支えます。
チップ面積・消費電力とのバランス設計
BGRは通常、回路の基本機能を支えるがゆえに、その性能を追求すると面積や電力を多く消費してしまいます。実際の設計では、面積や消費電力に厳しい制約がある場合、オペアンプレス型のBGRや電流量を低減した構成が採用されることもあります。レイアウト面では、回路要素の配置や金属配線層の活用によって、寄生成分の影響を抑えつつ面積を効率化する手法が取られます。また、低消費電力動作を実現するため、電源電圧のスケーリングやスリープ機能との協調設計が求められます。
実践例と先端技術
高精度プリアンプ、センサ信号処理、低電圧制御回路など、BGRは多くのアナログASICに応用されており、アーキテクチャや動作条件に応じて構成も多様化しています。広温度範囲対応の高次補償や、チョッパ方式によるドリフト低減など、用途特化型のBGR技術も登場しており、微小信号の安定化や省電力動作の実現に貢献しています。実装事例の蓄積により設計の選択肢も広がりつつあります。
ASICプリアンプなどにおけるBGRの応用例
センサ信号の微小な変化を検出するプリアンプ回路では、バイアス電流やオフセット電圧の安定性が極めて重要です。このような用途では、BGRはオペアンプや電流源の基準として機能し、温度変動や電源変動の影響を抑える役割を果たします。実際、地磁気センサや加速度センサの信号処理ASICなどでは、BGRを中心とした高精度なバイアス供給網が構成され、数μVレベルの微小信号を扱う上で欠かせない要素となっています。このような構成は、高精度計測回路の基盤技術といえます。
広温度範囲に対応する高次補償技術の活用
BGRの温度特性は、基本的なPTAT-CTAT打ち消し構成でも一定の安定性を得られますが、−40℃〜125℃といった広温度範囲においては、2次〜3次の温度補償技術が必要になる場合があります。これには、温度依存性を持つ電流源や抵抗の比率を温度に応じて可変に設計する手法が含まれます。さらに、カーブ補正技術として、温度特性の非線形性をあらかじめ想定し、設計初期段階で係数を最適化することも行われます。こうした技術により、高温・低温域でも±10ppm/℃以下の安定性を実現可能です。
オペアンプレス・チョッパ適用などの先端実装事例
低ノイズ・低消費電力が重視されるIoT向けアナログASICでは、オペアンプを使用しない構成や、チョッパ技術によるドリフト補償型のBGRが実装されています。オペアンプレス構成は、部品点数を削減しながらも、レイアウト対称性やカレントミラー構成の工夫により十分な精度を確保します。また、チョッパ方式は低周波ノイズを除去するため、センサ系回路と親和性が高く、広く応用されています。これらの実装技術は、アプリケーションに応じて最適なBGR構成を柔軟に選択するための設計引き出しとして有用です。
まとめ
BGRはアナログASICの基礎を支える回路であり、その精度や安定性が最終製品の信頼性に直結します。温度特性や電源耐性、長期ドリフトなど、多くの設計パラメータに対してバランスを取りながら最適化を行う必要があります。微細化や低電圧化が進む中で、BGRの設計技術も高度化し、プロセス変動への対応やオンチップ補正機能の導入が進んでいます。高信頼性を要求される分野では特にその重要性が高まっています。
アナログASIC設計におけるBGRの要点整理
BGRは温度や電源変動に対する耐性を持つ基準電圧源として、アナログASICの性能を支える中核的な役割を果たします。その安定性、ノイズ耐性、PVTばらつきへの対応力は、アナログ設計全体の品質を左右します。設計初期での仕様定義、トポロジ選定、レイアウト設計など、複数の観点から最適化が求められます。特に高信頼性アプリケーションでは、設計マージンの確保と長期安定性の評価が不可欠です。BGR設計は、アナログ回路開発の成功を左右する決定的な要素です。
設計品質・信頼性に直結するBGR設計の影響
BGRが不安定な場合、それに依存する回路ブロックも一様に性能劣化を引き起こします。たとえばADCのオフセット誤差増大、電源監視回路の誤動作など、製品全体の信頼性低下を招きます。逆に言えば、BGRの安定性を高めることで、全体設計における補正回路や冗長設計の負担を軽減し、シンプルかつ高性能な構成が実現可能となります。BGRの性能向上は、結果的に製品の長期信頼性と市場競争力に直結する戦略的要素となります。信頼性重視の回路設計では不可欠な観点です。
今後のBGR技術とアナログASICとの融合展望
今後、プロセスの微細化や低電圧動作が進行する中で、BGRにもさらなる進化が求められます。FinFETやFDSOIなど新しいCMOS技術への適応、オンチップトリミング技術の高度化、さらには自己診断機能を持つインテリジェントBGRなどが研究されています。また、システム全体の電源管理と連携するBGR制御機構の開発も進んでおり、アナログ設計とデジタル制御の融合が今後の設計トレンドとなる可能性があります。次世代ASIC設計におけるBGRの位置づけはさらに重要性を増していくと予想されます。
FeRAM搭載アナログASICの設計・開発サービスについて
https://www.ramxeed.com/jp/products/asic-assp/