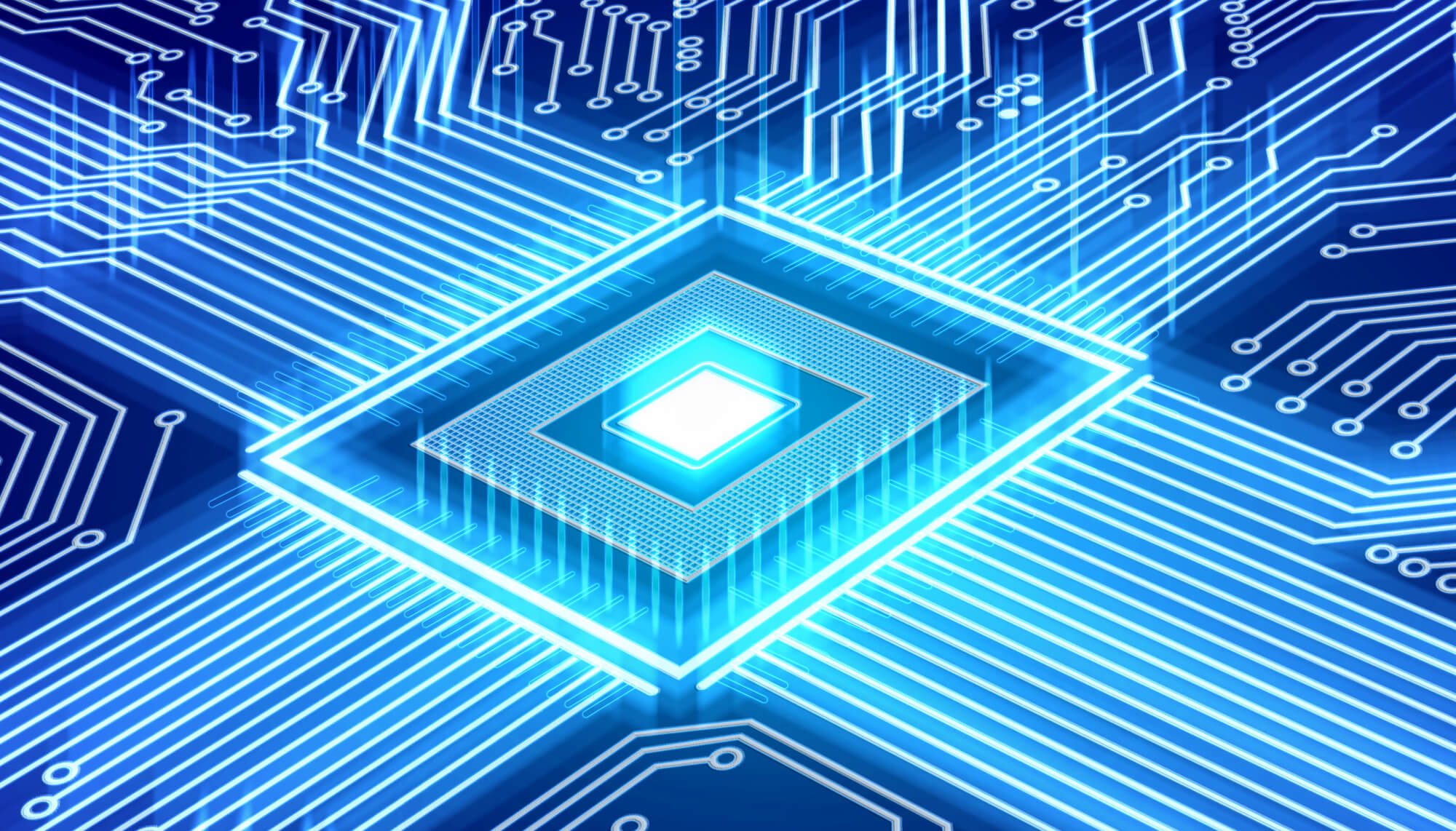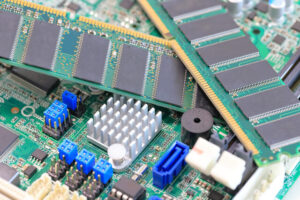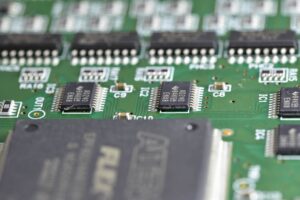アナログASICでワイヤレス給電を設計する際の技術要件と課題
アナログASICによるワイヤレス給電の設計技術を、方式別の特徴、回路ブロック構成、ノイズ・熱対策、プロセス制約まで網羅的に解説しています。IC設計エンジニアの実務に即した内容を中心に構成しています。
目次
ワイヤレス給電システムの基本方式とアナログASICに求められる性能・機能・制約条件
代表的なワイヤレス給電方式とそれぞれのアナログ回路構成の違い
ワイヤレス給電には電磁誘導方式、磁界共鳴方式、電界結合方式、RF方式など複数の方式が存在します。ASIC設計では特に、送電側・受電側のアナログ回路の構成がこれらの方式ごとに異なる点に注意が必要です。電磁誘導方式では、送受信コイルのインダクタンスに基づいた共振回路の調整が主となり、トランス構成のような高効率設計が可能です。一方、磁界共鳴方式は離れた距離でのエネルギー転送に適しており、共振周波数の高精度制御や結合係数の変動対応が求められます。方式の選定によってASIC設計の自由度や複雑性が大きく変化します。
アナログASICで必要となる主要性能指標とその最適化要件
アナログASICを用いたワイヤレス給電回路では、エネルギー変換効率、整流効率、負荷変動への応答性、伝送距離、EMI耐性など、複数の性能指標が同時に要求されます。たとえば効率を重視する場合、MOSFETのスイッチング損失を低減させる設計が重要になり、トポロジやレイアウトにも影響します。また、伝送距離とミスアライメント耐性のバランスをとるには、受電回路に高Q共振器を実装する必要があることもあります。これらの仕様達成には、アナログ設計とプロセス選定の両面から検討が必要です。
安全性・EMI・熱・非機能要件を設計段階でどう扱うか
ワイヤレス給電における非機能要件として、電磁波による周辺機器への影響(EMI)、過熱によるデバイス劣化、人体への影響などがあり、アナログASICの設計において無視できない要素です。特にEMI対策では、ドライバ回路のスイッチング波形の傾きを抑える設計や、シャントインダクタによる放射抑制などが必要です。また、熱設計では、電力密度の高い送電回路や整流回路において熱分布のシミュレーションとレイアウト設計が重要となります。これらの対策はアナログ回路設計者の経験とノウハウが反映される領域です。
ワイヤレス給電用アナログASICの構成ブロックと、それぞれの設計上の要点について
送電側(Tx)ASICの基本構成と高効率化のための設計技術
送電側ASICは、信号源、ドライバ回路、共振タンク回路で構成されることが一般的です。ドライバ段にはハーフブリッジ/フルブリッジ構成が使われ、低オン抵抗で高速スイッチングが可能なMOSFETの選定が重要になります。共振タンクはLC構成で、周波数と結合係数に応じたQ値の最適化が必要です。また、PWM制御や位相制御によって共振点を維持し、負荷変動への応答を確保する設計も不可欠です。高効率化の観点では、スイッチング損失と導通損失のバランス設計が中心課題となります。
受電側(Rx)ASICにおける整流・電圧変換・保護機能の統合
受電側ASICでは、共振回路から得られたAC信号を整流し、安定したDC出力を生成する役割があります。一般的にフルブリッジ整流と降圧型DC-DCコンバータが組み合わされ、さらに出力電圧制御、過電流・過電圧保護機能も集積されます。低ドロップアウト整流設計やシンクロナス整流の採用により、効率を向上させることが可能です。また、負荷に応じた適応制御を行うことで、無駄な電力損失を抑制し、システム全体の電力効率を最適化できます。これらをすべて1チップにまとめることがアナログASIC設計の挑戦です。
共振コイル、インダクタ、磁性部材など、周辺パッシブ要素との整合設計
アナログASICは単体では動作せず、共振コイルやインダクタ、磁性体など外付けパッシブ要素との調和設計が重要です。特に送受電コイルの位置関係、結合係数、インダクタンス値が共振周波数と効率に直結するため、回路と構造の両面から設計整合を取る必要があります。さらに、磁性部材の材質や形状によりEMIや磁束漏洩が変化し、ASICの動作点や安全規格への適合性に影響を及ぼします。設計段階でシステムシミュレーションを行い、アナログ回路と周辺要素の最適化を並行して進めることが成功の鍵となります。
アナログASIC設計で直面する技術的課題と、それに対する代表的な対策技術
プロセス選定と高電圧アナログ回路における設計上の制約
ワイヤレス給電用のアナログASICでは、高電圧動作が必要になるため、標準的なCMOSプロセスでは十分な耐圧や電力密度が得られないケースがあります。このため、高耐圧CMOS、BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)、SOIなどの特化プロセスの採用が検討されます。プロセスの選定により、トランジスタの特性、寄生容量、熱抵抗、レイアウト制約が大きく変わります。ASICの小型化と機能集積を進めるには、これらの制約の中で高効率・低損失なアナログ回路を成立させる技術が求められます。
高効率スイッチングとノイズ抑制の両立に関する設計上のジレンマ
高効率な電力転送を実現するためには、高速スイッチング回路が必要ですが、これに伴いEMIノイズやリンギングが発生しやすくなります。特にスイッチング周波数がMHz帯に入ると、EMC規格への適合が困難になります。これを防ぐためには、スルーレート制御、スナバ回路、ゲートドライバのチューニング、基板レイアウトの工夫など、多岐にわたる対策が必要です。高効率化とノイズ抑制はトレードオフ関係にあり、全体バランスを考慮した最適設計が求められます。
熱設計と放熱に関するアナログ回路レベルでの最適化手法
高出力を扱うアナログASICでは、自己発熱や誘導損失による温度上昇が避けられず、熱暴走や性能劣化を防ぐための熱設計が必須です。特にドライバ段や整流段では局所的に発熱が集中するため、レイアウト段階での熱経路の確保、金属層の最適配置、シリコン面積の調整が重要です。さらに、温度依存性のある素子特性(Vth、Ron、Cgsなど)を補償する回路も必要になります。パッケージの熱抵抗と外部ヒートシンクとの接続も含め、システム全体での熱最適化が求められます。
アナログASICによるワイヤレス給電応用の現状と、設計における重要な総括ポイント
製品応用事例に見るアナログASIC活用の方向性と実現可能性
現在、アナログASICを用いたワイヤレス給電技術は、医療機器、IoTセンサ、ウェアラブル端末など小型・軽量が求められる分野で実用化が進んでいます。これらの製品では、ASICを用いて送受電回路を高集積化し、回路全体の小型化とエネルギー効率向上を同時に達成しています。ASICによる設計は、回路特性の最適化だけでなく、EMC規格やバッテリ保護仕様にも対応しやすいという利点があります。ワイヤレス給電を単なる回路技術ではなく、システム最適化技術として捉えることが鍵です。
共振制御やアダプティブ電力制御など、進化する制御技術の導入例
近年では、共振周波数の自動追従制御や、受電電力のリアルタイム制御(アダプティブ制御)をASIC内で実装する事例が増えています。これにより、負荷やコイル位置の変動に対しても効率よく給電を継続できるようになります。制御にはオンチップのマイコンやDSPを用いる場合もあり、アナログフロントエンドとデジタル制御の連携が重要です。また、これらの制御回路が正確に動作するためには、高精度なアナログ信号処理と電源管理が必要であり、ASIC設計の難易度が一層増しています。
アナログASIC設計の観点から見た成功のポイントとチェックリスト
アナログASICによるワイヤレス給電を成功させるためには、以下の点を設計初期段階から網羅的にチェックする必要があります。①対象方式と伝送距離に応じたトポロジ選定、②プロセス技術の特性と制約の理解、③高効率/低損失回路設計、④EMI・熱・保護などの非機能要件対応、⑤外付け部品との協調設計、⑥制御アルゴリズムとの整合性。このようなチェックポイントをもとに、段階的に性能を積み上げることが、高品質なASIC実装への近道となります。
FeRAM搭載アナログASICの設計・開発サービスについて
https://www.ramxeed.com/jp/products/asic-assp/